思考停止しない!20代後半で後悔しない退職をする方法と、その後の健康保険・年金手続について大解説
「仕事を辞めたいけど、正しい判断なのかな?」
「その後の保険や年金の手続きもよくわからないし…」
「考えるのが面倒くさいから、このままでいいかも…」
と、思っている20代後半のそこのあなた!
ちょっと待って、そこで思考停止してしまうのは、危険です!!
考えることをやめると、あとで後悔することにもなりかねません。
今回は、あなたの「退職意思」としっかり向き合い、その後の保険・年金手続についても詳しく解説していきます。
面倒くさがりのあなたには、ぴったりの1記事となっております。
騙されたと思って、ぜひ最後まで読んでみてください!
注意!退職を決意する前に知っておきたいこと
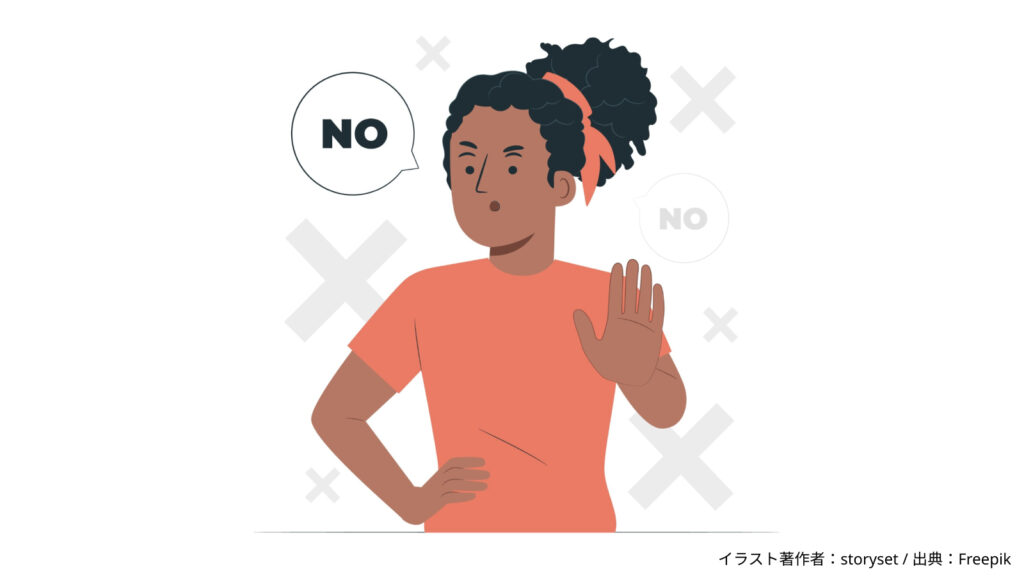
退職は、人生における大きなターニングポイントです。
結論を出すことは容易ではありませんが、ここでじっくり考えて出した答えが、あなたの未来を左右します。
まずはあなたの「辞めたい」気持ちと、きちんと向き合ってみましょう。
「辞めたい」理由を明確にする
なぜ、あなたは「辞めたい」と思っているのでしょうか?
- 人間関係
- 仕事内容
- 給料
という風に、思いつくことを書き出してみましょう。
誰かに話を聞いてもらうのも良いでしょう。
辞めたい理由を明確化する中で、
- 部署異動
- 上司との面談
といったことで、解決できる問題も出てくるかもしれません。
ここまで考えても、
「やっぱり、退職以外に選択肢がない…」
と思うのであれば、今度こそ、退職を決意するべきでしょう。

退職後の生活設計を立てる
あなたは退職後、何がしたいですか?
- ゆっくり休みたい
- すぐに転職活動を始めたい
- 独立・起業したい
など、人によって様々な選択肢があります。
どんな生活を送りたいかによって、
- 準備するべきこと
- 考えるべきこと
が変わってきます。
退職に乗り出す前に、今一度、その後の生活設計を具体的にイメージしてみましょう。

要チェック!退職後の健康保険と年金について

さて、退職の意思は固まってきましたか?
それでは次に、誰もが避けては通れない、退職後の健康保険と年金の手続きについて、分かりやすく解説していきます。
「なんだか難しそう…」と思っている方も、ご安心ください!
一つずつ丁寧に説明していきますので、ゆっくりと確認していきましょう。
健康保険の種類
退職後の健康保険には、主に3つの選択肢があります。
- 国民健康保険
市区町村が運営する健康保険。
退職後は自動的に加入にはならず、自分で手続きして加入する必要があります。 - 任意継続被保険者制度
退職前に加入していた会社の健康保険を、最長2年間、継続して利用できる制度。 - 家族の健康保険の扶養に入る
配偶者や親族が加入している健康保険の扶養に入ることも可能。
どれを選ぶかは、あなたの収入・家族構成・今後の予定によって異なります。
健康保険料を試算し、比較して検討するのがおすすめです。
健康保険の手続き
国民健康保険
お住まいの市区町村役所・区役所で手続きを行います。
【必要なもの】
- 退職証明書(または離職票)
- 本人確認書類
- 印鑑(または署名)
- マイナンバーがわかるもの
【ポイント】
- 退職日の翌日から14日以内に手続きする必要がある
- 保険料は前年の所得に応じて決まる
- 地域によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が必要
任意継続被保険者制度
退職前に加入していた健康保険組合、または協会けんぽに申請します。
【必要なもの】
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- 退職証明書または離職票 など
【ポイント】
- 退職日の翌日から20日以内に手続きする必要がある
- 退職前の保険内容をそのまま引き継げる
- 保険料は会社負担分も自己負担になるため、退職前より高くなる
国民健康保険より安い場合もあるため、両方の保険料を比較して選ぶのがおすすめです。
家族の健康保険の扶養に入る
家族が加入している健康保険組合や協会けんぽを通じて申請します。
【ポイント】
- 扶養に入るには、一定の収入要件(一般的に年収130万円未満など)を満たす必要がある
- 条件は健康保険組合ごとに異なるため、家族の勤務先で要確認
年金の種類
退職後の年金には、次の3つのパターンがあります。
- 国民年金
退職後、次の就職先が未定または自営業になる場合、国民年金の第1号被保険者に切り替えます。 - 家族の扶養に入る
配偶者が厚生年金または共済組合に加入しており、扶養要件(年収など)を満たす場合、第3号被保険者になります。 - 厚生年金
すぐに転職する場合は、転職先の会社が厚生年金の加入手続きを行います。
年金の手続き
国民年金
お住まいの市区町村の年金窓口で手続きを行います。
【必要なもの】
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職証明書または離職票
- 本人確認書類
- 印鑑(または署名)
【ポイント】
- 退職日の翌日から14日以内に手続きを行う
- 保険料は全国一律(毎年度変動あり)
【加入によって受けられる主な年金】
- 遺族基礎年金
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
家族の扶養に入る
配偶者などの勤務先を通して手続きを行います。
【ポイント】
- 扶養に入るには収入上限(一般的に年収130万円未満など)を満たす必要がある
- 必要書類や手続き方法は勤務先によって異なる
厚生年金
次の転職先が決まっている場合は、会社側が厚生年金の加入手続きを行います。
【ポイント】
- 自分で行う手続きは特にない
- 念のため加入状況を「ねんきんネット」などで確認しておくと安心
キャリアパスを設定し、退職を現実的に考える!

健康保険と年金についての疑問は晴れましたか?
それでは最後に、退職をもっと現実的なものとするため、その後のキャリアパスについて考えていきましょう。
転職
転職は、最も一般的なキャリアパスの一つです。
これまでの経験やスキルを活かして、新しい仕事に挑戦することができます。
転職活動を始める前に、
- 自分の強み・弱み
- どんな仕事が向いているのか
- どんな企業で働きたいのか
といったことを明確にしておきましょう。
転職エージェントに登録して、サポートに頼るのも一つの手です。
特に初めて転職する場合、利用はマストでしょう。

起業
起業すれば、自分のアイデアやスキルを活かして、新しいビジネスを始めることができます。
リスクは伴いますが、成功すれば大きなリターンも得られる、夢のある選択肢です。
- 国や自治体の支援制度
- 起業家同士の集まり
などを活用して、資金を集めたり、人脈を形成していくことが鍵となります。

スキルアップ
足りないスキルや、未知の分野について学ぶという選択肢もあります。
- 資格取得を目指す
- オンラインスクールに通う
- 海外留学
など、その方法は様々です。
スキルアップすることで、その後の転職や起業の可能性を広げることができるでしょう。
キャリアの選択肢は多種多様、これだけに収まらないでしょう。
しっかりと下調べをし、あなたに最善のキャリアパスを選択してください。

まとめ

このご時世、キャリアの変更は誰でも経験するものとなってきました。
若い人たちの間では、転職をしたことがない、という人の方が少ないのではないでしょうか。
起業する、フリーランスになる、海外へ飛び出す…
など、一昔前では簡単に選べなかった選択肢が、今はありふれている時代です。
この時代に産まれたチャンスを逃さず、自分が本当にやりたいことに、今この20代の若い時期だからこそ、ぜひチャレンジしてください。
老後の楽しみにとっておく…なんていう言葉、今は通用しませんよ。
あなたが勇気を出して、未来を変える行動を起こすこと、心から応援しています!



