【退職の決断】20代後半、スムーズな退職準備で円満に辞める秘訣を伝授!
「仕事を辞めたいけど、退職理由がネガティブなんだよな」
「こんな理由で辞めたいなんて言い出せない…」
「そもそも退職する時って、何をする必要があるんだろう?」
20代後半、こんな風に悩んで、一歩踏み出せずにいませんか?
今回はそんなあなたへ、
- 退職理由の伝え方
- 退職準備をスムーズに済ますコツ
をお教えします。
伝え方次第で、円満退社は可能です。
コツを掴んだら遠慮せず、堂々と退職しちゃいましょう!

退職理由、正直に伝えるべき?

退職を決意した時、必ずぶつかる壁。
それが「退職理由をどう伝えるか」問題です。
正直に話すべきか、それとも当たり障りのない理由にするべきか…悩みますよね。
結論から言うと、ケースバイケースですが、闇雲に正直に話すのが良いとは限りません。
ここでは、退職理由を伝える際のポイントを、あなたの状況に合わせて解説します。
正直に伝えるメリット・デメリット
まずは、正直に伝えることのメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
- スッキリする
溜め込んでいた不満を吐き出すことで、気持ちが楽になることがあります。 - 会社が変わる可能性
あなたの意見が会社の改善につながるかもしれません。(期待しすぎは禁物ですが…) - 円満退社につながる可能性
率直な意見を伝えたことで、会社との信頼関係が築かれ、円満な退社につながることもあります。
デメリット
- 引き止められる可能性
会社はあなたを失いたくないので、あの手この手で引き止めてくるかもしれません。 - 評価が下がる可能性
上司や会社への不満をストレートに伝えると、評価が下がる可能性があります。 - 退職交渉が難航する可能性
退職理由によっては、退職自体を拒否される可能性もゼロではありません。
正直に話すことは、必ずしも良い結果に繋がるとは限らないことを覚えておきましょう。
特に、感情的な言葉は避け、冷静に、論理的に話すことが大切です。
建前を使うのはアリ?
正直に話すのが難しい場合、建前の理由を使うのも一つの手段です。
例えば、以下のような答え方があります。
- キャリアアップのため
これは、非常に使いやすい理由です。現状の仕事では得られない経験やスキルを求めている、というニュアンスで伝えましょう。 - 家庭の事情
親の介護や、配偶者の転勤など、やむを得ない事情を伝えるのも有効的です。ただし、すぐにバレるような嘘をつくべきではありません。 - 体調不良
心身の不調を理由にする場合は、診断書などの証明が必要になる場合があります。
建前を使う場合は、矛盾点がないように注意しましょう。
突っ込まれた時に答えられるよう、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
建前を使うことは、決して悪いことではありません。
会社側も、社員の退職理由をすべて真に受けているわけではないでしょう。
お互いに、ある程度の「大人の対応」が必要になるというだけです。

退職理由別、伝え方の例文集

ここまでで「本音と建前を使い分けるべき」ということはわかりました。
「では、いざ退職理由を伝えよう!」
…と思っても、面と向かって伝えるとなると、緊張してしまいますよね。
このフェーズが苦手で、一歩踏み出せずにいる人も多いでしょう。
具体的にどのような退職理由を、どのように伝えれば良いのでしょうか?
ここではよくある退職理由別に、例文をご紹介します。
例文はあくまで参考として、自分の言葉で伝えるようにしましょう。
人間関係が理由の場合
現在の部署では、チームメンバーとのコミュニケーションが円滑に進まず、業務に支障をきたす場面がございました。
自身のスキル不足も痛感しておりますが、より協力的な環境で成長したいと考えております。
- 具体的なエピソードは避ける
- 自分のスキル不足にも触れることで、謙虚さをアピールする
- 前向きな言葉で締めくくる
給与・待遇が理由の場合
現在の給与水準では、今後のライフプランを考えると厳しい状況です。
自身の市場価値を考慮し、より待遇の良い企業でチャレンジしたいと考えております。
- ストレートに「給料が低い」とは言わない
- 自分の市場価値をアピールする
- 将来を見据えていることを伝える
仕事内容が理由の場合
現在の業務内容では、自身のスキルや経験を十分に活かすことが難しいと感じております。
より専門性の高い○○の分野で、自身の能力を最大限に発揮したいと考えております。
- 現状の仕事内容を否定しない
- 自分のスキルや経験をアピールする
- 具体的なキャリアプランを伝える
体調不良が理由の場合
昨年から体調を崩しやすく、医師からも休養を勧められております。
まずは、心身ともに回復に専念し、体調が万全になった状態で、改めて社会に貢献したいと考えております。
- 無理をしていることをアピールする
- 休養が必要であることを伝える
- 復帰への意欲を示す
これらの例文を参考に、あなたの状況に合わせた伝え方を考えてみてください。
退職理由を正直に伝えるべきか、建前を使うべきか。
そこには、
- あなたの現職での立場
- 会社や上司との関係性
- 今後もどこかで一緒に仕事をする可能性があるかどうか
など、さまざまな見極めポイントがあります。
自分の現状を把握し、円満退社を心がけ、本音と建前を使い分けましょう。

退職準備をスムーズに進めるためのコツ
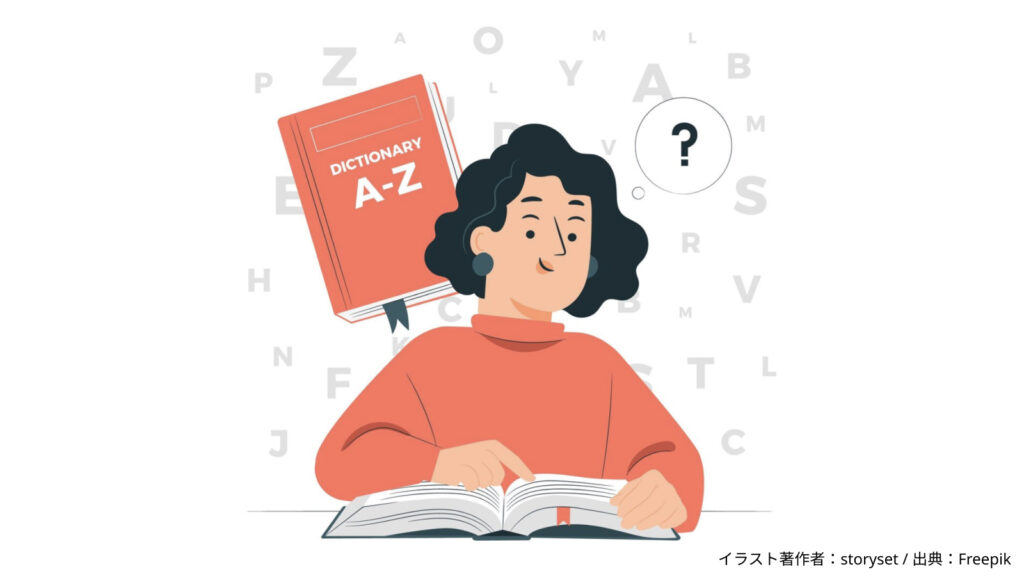
退職を伝えるだけでも勇気がいるのに、いざ退職準備となると、気が重くなりますよね。
でも、大丈夫!
事前の準備と心構えで、退職準備はスムーズに進めることができます。
以下で、そのコツをご紹介していきましょう。
退職の意思は早めに伝える
退職の意思は、できるだけ早く会社に伝えましょう。
法律では、退職日の2週間前までに伝えれば良いとされています。
しかし、会社の規定や業務の引継ぎなどを考慮すると、1~2ヶ月前に伝えるのが理想的です。
会社側は後任の選定や引継ぎの準備をする必要があるため、迷惑のかからないよう早めに伝えるべきです。
そして、あなた自身も余裕を持って退職の準備を進めることができます。
退職日は明確に伝える
退職日は、明確に伝えましょう。
「〇月頃」といった曖昧な表現ではなく、「〇月〇日」と具体的な日付を伝えることが大切です。
退職日が決まっていれば、会社も引継ぎの計画を立てやすく、スムーズに後任へと引き継げます。
そして、あなたの退職意思が固いことも伝えられるため、無理に引き止められる可能性も少なくなるでしょう。
引き継ぎはしっかりと行う
退職が決まったら、引き継ぎはしっかりと行いましょう。
後任者が困らないように、業務内容や手順、注意点などを丁寧に説明することが大切です。
引き継ぎ書の作成も、後任者にとってはありがたいでしょう。
引き継ぎをしっかりと行うことで、会社からの信頼を得ることができ、円満退社につながっていきます。
有給休暇の消化について
退職前に、有給休暇の消化についても確認しておきましょう。
法律では、有給休暇は労働者の権利として認められています。
しかし、会社の規定や業務の状況によっては、希望通りに消化できない場合もあります。
事前に会社と話し合い、有給休暇の消化スケジュールについて合意しておくことが大切です。
退職後の手続きについて
退職後には、様々な手続きが必要になります。
雇用保険や健康保険、年金など、手続きの種類は多岐にわたります。
会社から必要な書類を受け取り、漏れがないように手続きを進めましょう。
退職後の手続きについては、会社の担当部署に確認するのが確実です。
退職準備は、誰にとっても多大なエネルギーを使う作業です。
これらのコツを駆使し、最小限のエネルギーで、円満退社へと繋げていきましょう!

辞めた後のキャリアパス、どうする?

退職意思の告げ方と、退職準備をスムーズに進めるコツは掴めましたか?
それでは最後のステップとして、退職後の人生について考えてみましょう。
現代では会社に勤める以外にも、さまざまな選択肢があります。
一度きりの人生、せっかくなら自分の心が踊る選択をしてみましょう。
転職
最も一般的なキャリアパスが、転職です。
転職活動は、できれば在職中に行うのが理想的です。
しかし、退職後にじっくりと時間をかけて探すのも一つの選択肢です。
転職エージェントを利用すれば、一人で不安な方でも安心して転職活動に臨めます。
転職活動全般のサポートをしてくれる、心強いパートナーとなるでしょう。
独立・起業
「自分の力で何かを成し遂げたい!」という方は、独立・起業という道もあります。
リスクは伴いますが、成功すれば大きなリターンを得ることができます。
しっかりと事前準備をし、綿密な計画を立てることが大切です。
独立した人や、起業家のコミュニティ・セミナーなどにも顔を出してみましょう。
人脈を作ることが、その後の仕事の受注につながっていくでしょう。
スキルアップ
退職を機に、スキルアップを目指すのも良いでしょう。
資格取得を目指したり、セミナーや講座を受講することで、自分の市場価値を高めることができます。
転職活動にも有利に働きますし、将来的なキャリアの可能性を広げることができます。
休息
「仕事に疲れてしまった」という方は、休息をとるのも良いでしょう。
旅行に行ったり、趣味に没頭することで、心身ともにリフレッシュすることができます。
休息は、次のステップに進むための充電期間です。
「怠けているのでは」と罪悪感を持つ必要は全くありません。
次の明るいキャリアのためにも、思いっきり自分を労りましょう!

まとめ

「退職したい」と会社に伝えることは、なかなか容易にできることではありません。
それでもそこで勇気を持つことが、あなたの新たな可能性への「鍵」となります。
その「鍵」を手にできたならば、あとは進むべき扉に向かって突き進むのみ!
自分の気持ちに正直に、後悔のしない未来を掴んでください。
あなたの退職、そしてその後の新しいキャリアを、心より応援しています!



